直前対策の収益不動産投資の否認事例から学ぶこと

※この事案は、令和4年4月19日に下された最高裁判所の判決により、納税者の敗訴が確定しました。
昨年に続き、今年も相続直前の対策として、収益不動産を購入することで大幅に相続税を減額させて申告された納税者が裁判で敗訴しました。この事案は令和2年11月に東京地裁で納税者が敗訴し、納税者が控訴しておりましたが、令和3年4月に東京高裁でも敗訴が確定しました。現在納税者は最高裁判所へ上告しているようですが、敗色濃厚と考えられています。このブログをお読みいただければ、相続税の対策(特に直前対策)を行う上で注意すべき点が理解できます。
1.今回の事案の概要
相続人 (控訴人・被相続人の長男、長女、二男) は、平成25年9月、父親である被相続人が売買価格15億円で購入した法人向けの単身者用高級賃貸マンション (以下、本件不動産)を相続で取得しました。
被相続人らは、生前から銀行との間で本件不動産の購入等による相続税の圧縮効果等を検討しており、被相続人は、平成25年6月に肺がんが発覚した直後、銀行から15億円を借入れた上で本件不動産を購入していました。
本件不動産について、相続人が、評価通達に基づき「4億7,761万1,109円 (通達評価額)」と評価し、借入金15億円を債務として計上した上で相続税の申告を行ったところ、国が、評価通達6項を適用し、本件不動産の評価額は「10億4,000万円 (鑑定評価額)」であるとして、相続税の更正処分等を行ったことで争いとなりました。
争点は、本件相続開始時における本件不動産の時価 (評価通達の定めによらない評価方法により本件不動産の時価を算定することが許されるか否か) です。
2.地裁・高裁の判断内容
(1)東京地裁の判断内容
| 本件では、① 通達評価額と鑑定評価額との間に著しいかい離が生じていること、② 相続税の負担減少を認識・期待して本件不動産が購入されたことから、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することができないなど、租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような「特別の事情」がある。よって本件不動産の時価は、評価通達6項に基づく鑑定評価額10億4,000万円となる。 |
(2)東京高裁の判断内容
東京高裁は、一審の東京地裁の判断を支持し、本件不動産の時価は、評価通達6項に基づく鑑定評価額10億4,000万円と認定しています。
さらに、相続人からの補充的主張に対する高裁の判断は、下記の通りです。
| <相続人の主張①> どのような場合に評価通達に定める評価方法以外の方法によって財産の価額を評価するかについての基準が明らかでなく、本件更正処分は、国民の租税に対する予測可能性を著しく失わせる不当なもの。租税法律主義の趣旨に反し、評価通達6項の適用に関する行政庁の裁量の範囲を著しく逸脱するものである。 <東京高裁の判断①> 租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな場合についてまで、評価通達の定めにより評価すべきものではないし、そのような場合について評価通達の定めによらないで個別に財産を評価したとしても租税法律主義に違反するということはできない。被相続人は、相続税を減少させる目的で本件不動産を相続開始の直前に15億円で購入していたのであるから、評価通達の定めによる評価額と現実の取引価格との間に著しいかい離があることは十分認識していたというべきであり、現実の取引価格によって課税されることについて予測可能性がなかったということはできない。 |
| <相続人の主張②> 評価通達の定めによる評価額と実際の取引価格との間にかい離がある例は多数存在し、かい離の存在は一般的な現象である。 <東京高裁の判断②> 本件不動産の通達評価額は、鑑定評価額の2分の1にも達しておらず、金額にして5億円以上も少ないから、そのかい離の程度は著しいといわざるを得ないところ、このような著しいかい離の存在が一般的であると認めることはできない。 |
| <相続人の主張③> 相続に際し、節税対策をとることは当然であり、被相続人が節税目的で本件不動産を購入したとしても、そのことが「特別の事情」を基礎づけるものではない。被相続人が本件不動産を購入したのは不動産賃貸業の一環であり、相続税対策のためではない。 <東京高裁の判断③> 被相続人が相続税の圧縮を認識し、これを期待して15億円を借入れ、本件不動産を購入したことは、租税負担の実質的な公平という観点から見た場合、通達評価額によらないことが相当と認められる「特別の事情」を基礎づける事実に当たるというべきである。被相続人らは、銀行の担当者と相続税の負担軽減の方法について相談し、その方策として、本件不動産を購入することになった経緯を踏まえると、本件不動産の購入が相続税対策のためであったことは明らかである。 |
3.この判決の影響
判決文を見ると納税者の主張が一蹴されています。余程自信のある判決かがうかがい知れます。この判決の及ぼす影響は甚大です。
今後の相続申告実務はどのようにしたら良いのでしょうか?取得価額に比べて相続税評価額が1/3まで下がることはよくあります。また1/2ならどうなのかもはっきりしません。
最高裁判決が出れば、何らかの判断基準が国税庁からも示されるかもしれませんが、ことの性格上示されない可能性もあります。
我々としては税務否認されるかどうか分からないものを、あえて取得価額に近い時価で相続申告をするという選択はありえないと考えます。
税理士としてはリスクの説明をして申告をして頂けば済むことですが、相続人の方々は否認されれば、本税以外に、加算税、延滞税を上乗せされ大変なことになります。またそれ以上に後日追徴税額が出れば、相続人全員の相続税負担が増え、その負担を誰がするのかという深刻な問題に繋がります。それでは、どう申告すればよいのでしょうか?
そこでさらに、この事件の背景を詳しく探り、対策を考えたいと思います。
4.その後判明した事案の概要
平成24年4月頃
銀行との間で相続税対策についての相談が開始
同年5月
相続税の総額を計算した相続税概算計算書を銀行から受領
平成25年6月
被相続人が肺がんにり患していることが発覚、同年6月6日銀行支店担当者から、節税対策として即効性のある中古物件の購入を勧奨され、物件の紹介を受けることを決定
同年6月19日
不動産業者を紹介され、購入により相続税評価額が9億円減少し、相続税を約3億円圧縮できる旨の説明
同年7月12日
銀行支店及び業者担当者らとの打ち合わせで、不動産購入を決め、価格交渉の結果、売買価額を15億円とする買付証明の差入れ
同年7月25日
業者との間で、不動産を15億円で購入する旨の売買契約を締結
同年8月20日
銀行から、賃貸不動産購入資金として、15億円を借入れ
同日
不動産につき、売買を原因とする所有権移転登記
同年9月16日
89才で死亡 (売買契約から2ヶ月未満で亡くなられています)
平成26年7月1日
相続税申告 (当初申告)
平成27年8月14日
被相続人の配偶者死亡
平成28年11月14日
対象土地以外の土地の評価誤りにつき修正申告
平成29年11月22日
東京国税局内で評価通達6に基づく評価を行う旨上申
平成30年5月28日
更正処分等
5.この事案の特殊性
① 本件は神奈川県の案件で、取得価額からすると3分の1程度まで圧縮されていること
② 物件購入から、相続開始までの期間が2か月にも満たないこと
③ 銀行内の稟議書に「相続税対策」のためということが書かれていること
このことを裏付ける判決文があります。
| 本件被相続人や原告らが本件不動産を購入した主たる目的は収益性の確保と不動産賃貸業の維持にあり、相続税対策を主眼としたものではなく、○○銀行□□支店の担当者が作成したメモには「相続税対策」などの文言もあるが、これは銀行内部での稟議を通すため、あるいは営業トークとしての表現にすぎないなどと主張する。(東京地裁令和2年11月12日判決文より) |
④ 被相続人は死亡時89才だったこと
⑤ 申告期限から4年も経過してから更正が行われているが、これは被相続人死亡後に、配偶者が亡くなり、この配偶者の相続税申告の準備中に、先の相続税申告のミスに気が付き修正申告をしたことが引き金になったと考えられること
6.まとめ
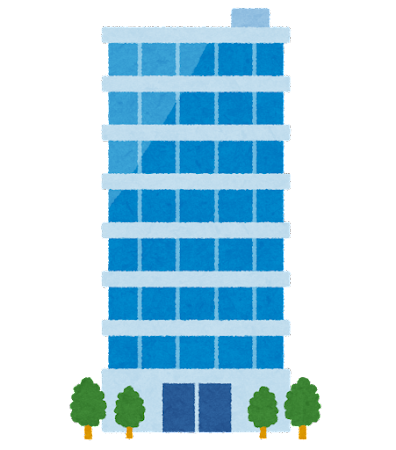
お幾つになられても不動産物件を取得するのはいけないということにはなるはずがなく、その投資による節税効果が大なり小なりはあるもので、そのかわりに空室や値下がりのリスクもあるものです。したがって今後も不動産投資は断念する必要はありません。ただ行き過ぎた節税と見られるものには国税当局がかなり神経質になっていることも確かです。
まだ明確な対応策は浮かびませんが、少なくとも相続直前には大きな対策をしないこと、銀行員には稟議書に「相続税対策」という言葉は一切書かないように依頼すること、そのあたりが信用できない銀行員の勧めでは物件を取得しないことでしょう。
今回の事件では、銀行が融資をする際に作成した資料が全て、納税者の租税回避の意図を立証する資料として使われています。従って銀行員に対しても「目的は、不動産事業を拡大・安定させるため」と言い続けること、節税効果を記載した書類は自宅からも処分しておくこと、もちろん相続後直ぐには物件を売却しないこと、などに注意をする必要がありそうです。

